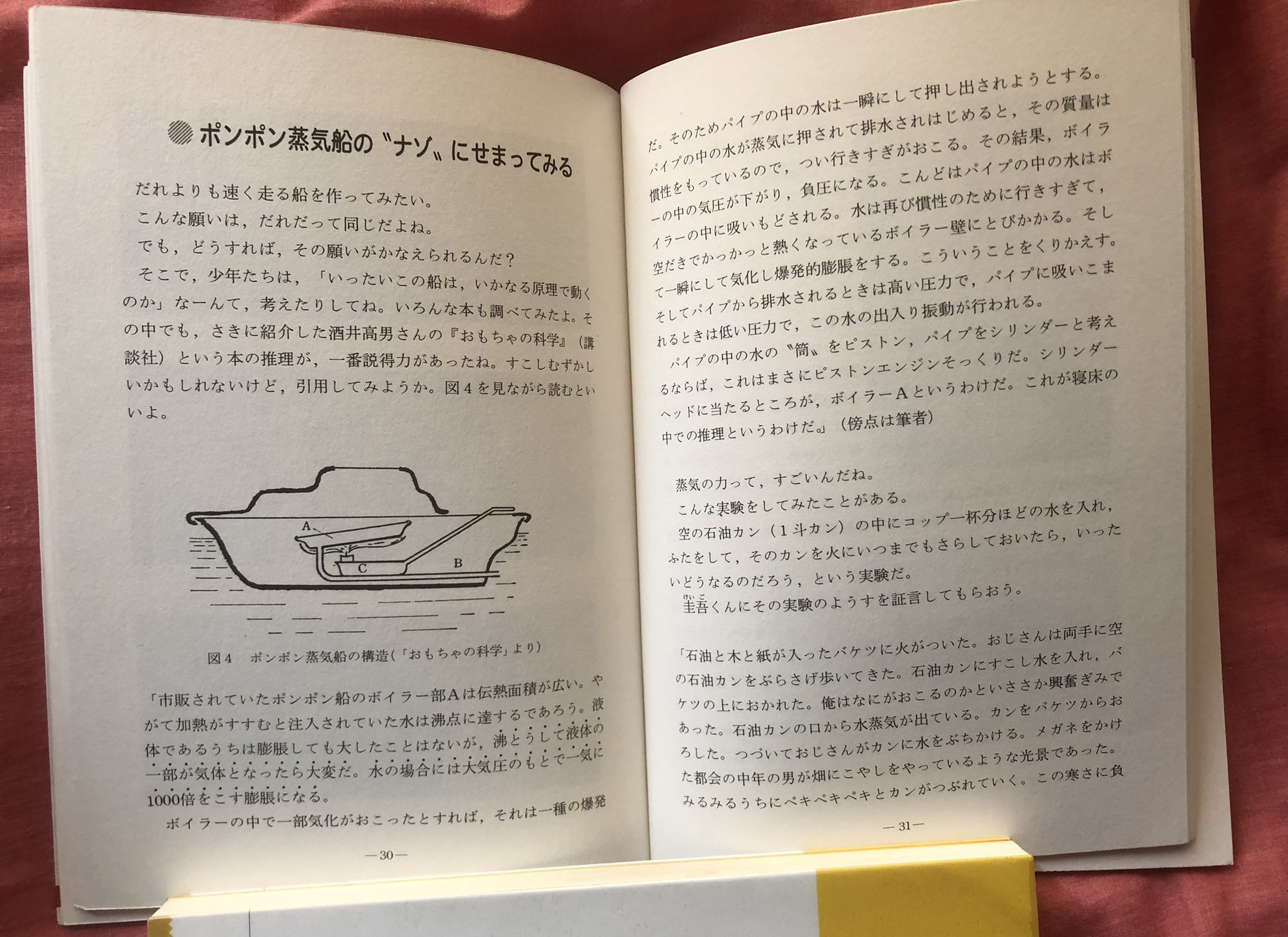
◆しかし、疑問もある。
・ろうそくの小さな火力で噴射ということが起きるのか。 ・1秒間に2、3回くらい起こっているようだが、わずかの火力で本当にこんなことが起きるのか。 ・なぜゆっくりと定常的に蒸発しないで、噴射と冷却が繰り返す振動が起きるのか。 それを説明する文献もみあたらない。 ◆検討 そこでどんな現象が起きているか仮定をしながら試算してみた。 1回で、水が0.012cm3沸騰する。(直径1.25mmの水滴相当) (試算するとこれくらいの量だと思われる) これが沸騰すると、1700倍の2cm3になる。 噴出官の内径が4mmとすると、長さ6cmx(2本)に相当する。 また沸騰は1秒間に3回起きるとして、1回当たり0.012cm3が沸騰するのに必要な火力は、9J/sec(W)である。 (540cal/g+1cal/gx60℃)x4.2J/calx0.012gx3回/s) ろうそくの火力は50Wといわれている。この試算では、ろうそくの18%の火力がポンポン船の水の蒸発に使われることになる。 注)いろんな文献を見ると「沸騰」と言う言葉を使わず「蒸発」と言う言葉を使用しているようです。しかし、100℃で蒸発して噴出するという現象から「沸騰」と言う言葉をここでは使います。 熱は周りの空気や水に、かなり逃げていて効率は悪いように思われる。(下記実験でそれが推定される) なぜ沸騰が断続して起こるのか、周波数はなんで決まっているのかなどはよくわからん。 ◆実験 試しにビールのアルミ板をろうそくで熱してみた。

表面温度計でアルミ板の温度を測ると、測った温度は160℃くらいが最高だった。思ったより低い。水滴をアルミ板に落とすと、一瞬「ジュッ」と言う音が出て、沸騰した。炎と水面の中間部は、60℃くらいまでしか上がらなかった。 戻る